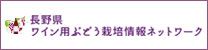研究成果『病害虫』
長野県農業関係試験場にて取り組んだ「病害虫」の研究内容とその成果をご紹介します。
|
試験して得られた技術事項 平成13年(2001年)野菜試
セルリー萎黄病に対する熱水土壌消毒法の適応性その2Fusariu moxysporumによって引き起こされる萎黄病は、セルリー栽培において最も深刻な生産阻害要因となる土壌伝染性病害である。現状、産地では、クロルピクリンによる土壌消毒で防除しているが、本剤は処理時の作業者に対する刺激が強いことから代替薬剤や耕種的防除方法の要望が強い。近年、農林水産省農業研究センターにより開発された熱水を利用した土壌消毒法は、トマト萎凋病やホウレンソウ萎凋病等のフザリウム菌による土壌病害に対する防除の有効性が明らかにされている。そこで、熱水土壌消毒法のセルリー萎黄病に対する適応性について検討する。 |
|
試験して得られた技術事項 平成13年(2001年)野菜試
スイカ炭腐病(仮称)菌、Macrophominaphaseolinaの寄主範囲日本国内のウリ科野菜で初発生したスイカ炭腐病(仮称)は、多犯性植物病原菌であるMacrophomina phaseolinaによって引き起こされる土壌伝染性病害であることが明らかとなった。今のところ発病面積は少ないものの,本病原菌は典型的な多犯性土壌病原菌であり、休耕地に作付する作物や輪作作物の選定には注意を要する。そこで、本病菌の寄主範囲について検討し、防除対策の資料とする。 |
|
試験して得られた技術事項 平成13年(2001年)野菜試
レタス斑点細菌病の病徴判別法レタス斑点細菌病は近年発生が増加しているが、外葉葉縁部が褐変する症状は斑点細菌病菌が関与するものと生理的要因によるものがあり、診断に迷う場合がある。そこで斑点細菌病と、斑点細菌病以外の要因による葉縁部褐変症状の違いを明らかにし、効率的防除の資とする。 |
|
試験して得られた技術事項 平成13年(2001年)野菜試
スライド凝集反応を利用したスイカ果実汚斑細菌病菌の検出法平成11年に本県における初発生が確認されたスイカ果実汚斑細菌病は、今後も再発生する可能性がある。発生を確認するためには正確な診断が必要だが、本病の葉における病徴は生理障害や褐斑細菌病と類似する場合があり、現場で適用できる簡易な検定技術が必要である。そこで農業技術研究機構野菜茶業研究所で開発された感作液を用い、本病菌Acidovorax avenae subsp. citrulli(Aac)のスライド凝集反応法による検出技術を検討する。 |
|
試験して得られた技術事項 平成13年(2001年)野菜試
培地によるレタス根腐病菌のレース判別法レタスから分離したF.oxysporum f.sp. lactucaeには2つのレースが存在するが、レース判別には従来多くの時間および労力を要する接種試験を行う必要があった。本病菌のレース1とレース2では、レースに特異的な栄養要求性の差が認められたことから、その性質を利用した簡便なレース判別法を開発し、抵抗性品種の効率的利用をはかる。 |
|
試験して得られた技術事項 平成13年(2001年)南信試
マルメロの尻腐れ症状の原因究明と防除対策マルメロ栽培で収穫期に果実のていあ部から腐敗が進行する尻腐れ症状が問題となっている。この尻腐れ症状の原因を究明するとともに防除対策を検討する。 |
|
試験して得られた技術事項 平成13年(2001年)南信試
日本なし「幸水」で問題となる心腐れ症状の発生生態と防除対策主に「幸水」で発生する心腐れ症状は、収穫時あるいは選果時に外見から判別できないものが多いため、市場や消費者段階で初めて顕在化することが多い。これらはクレームとなり、産地のイメージを著しく落とす原因となる。この心腐れ症状の原因と発生生態を解明し、防除対策を講ずることにより心腐れによる被害を軽減する。 |
|
普及技術 平成13年(2001年)水産試験場 水産試験場佐久支場
新しい農薬の魚類に対する急性毒性(H.13)魚類に対して、ホライズンドライフロアブル、デラウス粉剤DLは急性毒性があり、基準散布濃度で使用した場合でも魚類に被害を及ぼすおそれがあるので、使用に当たっては注意を要する。デラウスフロアブル、インダーフロアブル、バリアード顆粒水和剤、マトリックフロアブルの魚類に対する毒性は低い。 |
|
普及技術 平成13年(2001年)南信農業試験場
新しい農薬の蚕に対して薬害のなくなる安全基準日数(H.13)新しい農薬の蚕に対して薬害のなくなる安全基準日数は、デラウス粉剤DLが1日、デラウスフロアブルが1日、マイトコーネフロアブルが3日、スカーラフロアブルが3日、マトリックフロアブルが60日以上、ホライズンドライフロアブルが21日である。 |
|
普及技術 平成12年(2000年)水産試験場 水産試験場佐久支場
新しい農薬の魚類に対する急性毒性(H.13)魚類に対して、イノーバ1キロ粒剤51、マッチ乳剤は急性毒性があり、基準散布濃度で使用した場合でも魚類に被害を及ぼすおそれがあるので、使用に当たっては注意を要する。 |
|
普及技術 平成12年(2000年)野菜花き試験場
TSWV(トマト黄化えそウイルス)によって野菜花き類に発生するウイルス病は、イムノクロマト法により簡易診断できるTSWVによって野菜花き類に発生するウイルス病は、イムノクロマト法(米国Agdia社製,商品名:ImmunoStrip)を利用することにより、簡易診断できる。ただし、病徴(えそ、黄化、輪紋症状など)が見られる検体に限る。 |
|
普及技術 平成12年(2000年)農事試験場
イネばか苗病、苗いもち、もみ枯細菌病(苗腐敗症)、苗立枯細菌病防除に温湯処理が有効であるリンゴ輪紋病・炭疽病の防除にダイパワー水和剤の1000倍液を散布する。芽出し2週間後から落花25日後ごろまではさび果を生じるおそれがあるので使用しない。 |
|
試験して得られた技術事項 平成12年(2000年)野菜試 中信試
レタス根腐病菌の汚染拡大要因レタス根腐病の発生圃場面積は拡大しつつあり、病原菌の圃場間伝播が生じていると考えられる。病原菌の伝播をもたらす要因としては、風食により飛散する土壌、育苗段階における苗に対する病原菌汚染、トラクターに付着した土壌の移動等が考えられる。そこでこれらの要因を確認するため、風食土壌及び育苗施設床土から病原菌の検出を試みる。さらにトラクターから剥離した汚染土壌の有効な殺菌方法について検討する。 |
|
試験して得られた技術事項 平成12年(2000年)野菜試
レタス葉面から分離した拮抗細菌接種によるレタス腐敗病の発病抑制レタス腐敗病の発生は、大きな生産阻害要因になっている。防除薬剤の銅剤、ストレプトマイシン剤等は薬害の発生する危険性や収穫前使用日数の制限により、防除可能な期間が短く、防除効果も不十分である。また銅剤、ストレプトマイシン剤に対する耐性菌の存在も確認されている。さらに環境保全型農業推進から化学農薬の使用はできるだけ控えることが望ましいと考えられる。そこでレタス葉面細菌を利用したレタス腐敗病の生物防除技術を開発する。 |
|
試験して得られた技術事項 平成12年(2000年)南信試
きゅうりのウリノメイガに対する数種薬剤の防除効果近年南信地方のきゅうりを中心に、ウリノメイガの多発が問題となっているが、県の防除基準には採用されていなかったので、他害虫の防除で採用されている殺虫剤の効果を検討した。 |