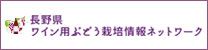研究成果『病害虫』
長野県農業関係試験場にて取り組んだ「病害虫」の研究内容とその成果をご紹介します。
|
試験して得られた技術事項 平成12年(2000年)農総試 果樹試
アメダス気象情報を利用したリンゴ黒星病感染予測情報提供システム果実に深刻な被害をもたらすリンゴ黒星病の感染好適条件を把握するために、アメダス気象情報を利用したリンゴ黒星病感染予測情報提供システムを構築した。このシステムから得た情報を基に、適期に効率的なリンゴ黒星病防除を行うことを目的とした。 |
|
普及技術 平成12年(2000年)水産試験場 水産試験場佐久支場
新しい農薬の魚類に対する急性毒性(H.12)魚類に対して、イオウフロアブル、オリブライト1キロ粒剤、カーゼートPZ水和剤、デラウス粒剤、パスワード顆粒水和剤、ペンコゼブフロアブル、マイトコーネフロアブル、モンカットフロアブルは急性毒性があり、基準散布濃度で使用した場合でも魚類に被害を及ぼすおそれがあるので、使用に当たっては注意を要する。スカーラフロアブルの魚類に対する毒性は低い。 |
|
普及技術 平成12年(2000年)南信農業試験場
新しい農薬の蚕に対して薬害のなくなる安全基準日数(H.12)新しい農薬の蚕に対して薬害のなくなる安全基準日数は、カネマイトフロアブルが1日、プラウ水和剤が7日、カーゼートPZ水和剤が7日、パスワード顆粒水和剤が1日、イオウフロアブルが3日、モンカットフロアブルが日である。 |
|
試験して得られた技術事項 平成12年(2000年)野菜花き試験場
苗箱への薬剤灌注散布によるキャベツのコナガ防除近年,キャベツ,はくさい,レタスなどでは育苗にセルトレーを用いるセル成型育苗がおこなわれている。さらに大規模育苗センターによるセル育苗がおこなわれている。また害虫防除の面では,定植時の粒剤の植穴処理が普及している。しかし,この処理は労力がかかり,実用面では問題がある。育苗期後半の粒剤処理も登録が増えてきているが,簡便な方法ではない。そこで,省力的で効果の高い防除方法を開発する。 |
|
試験して得られた技術事項 平成12年(2000年)果樹試験場
リンゴ黒星病発生予察器Metos-Dによる感染予測の適合性リンゴ黒星病発生予察器の感染予測の適合性を検討する。 |
|
試験して得られた技術事項 平成11年(1999年)南信農業試験場
ナミハダニの農薬に対する感受性簡易検定法現場で直面しているナミハダニの農薬に対する感受性について、特別な実験器具を持たない農家や現場の指導者が、大まかな傾向をつかむための安価で簡単な検定方法を開発する。 |
|
試験して得られた技術事項 平成11年(1999年)野菜花き試験場
トマトのハダニ類に対するケルセン乳剤の効果ここ数年,トマト栽培圃場で,ハダニ類の発生が問題となっている。これまでトマトではあまりハダニ類が発生しなかったことから,登録薬剤はほとんどない。また,トマトでは,発生初期の葉への症状が明瞭でないため,発生の確認が遅れて多発状態になりやすい。また,ミニトマトでは金粉症状を引き起こす原因の1つとなる可能性がある。そこで,ハダニ類の防除対策を検討する。 |
|
試験して得られた技術事項 平成11年(1999年)果樹試験場
導入天敵チュウゴクオナガコバチによるクリタマバチの防除効果平成4年に小布施町において放虫した導入天敵チュウゴクオナガコバチの県内分布の拡大と防除効果について調査する。 |
|
試験して得られた技術事項 平成11年(1999年)営農技術センター 野菜花き試験場
レタス根腐病菌Fusariumoxysporumf.sp.Lactucae各菌株の病原性差異レタス根腐病はFusarium属菌に起因する土壌伝染性病害で,本県のレタス生産において脅威となっている病害である。本病の防除法として,抵抗性品種の利用が最も有効であるが,病原菌のレタス品種・系統に対する病原性についての知見はほとんどない。今後,抵抗性品種育成を行う上で,この点の検討が必要と考えられたことから,発病が確認された県下3地区から分離した菌株のレタス品種・系統に対する病原性について検討した。 |
|
試験して得られた技術事項 平成11年(1999年)野菜花き試験場
2作1回施肥マルチ栽培輪作体系によるハクサイ根こぶ病の防除連作障害の回避と、廃プラスチック問題の解決及び省力、低コスト化等を目的として、2作1回施肥マルチ栽培における輪作体系が増加している。この時後作に、はくさいを栽培する体系でハクサイ根こぶ病の発病が抑制される現象が見られたので実証した。 |
|
試験して得られた技術事項 平成11年(1999年)果樹試験場
オニグルミはリンゴ炭疽病の伝染源となるニセアカシア,シナノグルミがリンゴ炭疽病の伝染源植物となっていることが明らかとなっている。平成11年の現地調査の結果,山林や河川敷に自生しているオニグルミの近傍のリンゴ園でも炭疽病の発生がみられた。そこでオニグルミが伝染源となりうるか検討する。 |
|
試験して得られた技術事項 平成11年(1999年)農事試験場
DMI剤混用による無機銅剤のもみ枯細菌病に対する防除効果の低下スターナ耐性もみ枯細菌病菌の出現により、種子消毒剤として銅剤の使用が増えると予想される。銅剤は細菌病に効果はあるものの、いもち病、ばか苗病といった糸状菌病害に対して効果がないため、DMI剤(EBI剤)、あるいはベノミル剤と混用して使用される場合が多い。一方、DMI剤の単用処理は、もみ枯細菌病の発病を助長することから(平成7年の得られた技術事項)、DMI剤あるいはベノミル剤と混用した場合の無機銅剤の効果を検討する。 |
|
試験して得られた技術事項 平成11年(1999年)野菜花き試験場
レタス根腐病の発病における品種間差異レタス根腐病は1995年の発生以来発生面積を拡大し、本年度は約59haの発生が確認されている。被害軽減の緊急対策として、薬剤防除及び輪作などの耕種的防除が試みられている。さらに長期的視野にたって抵抗性品種の育成にも着手している。そこで育種素材としての利用及び耕種的防除法での利用を念頭に置き、国内で市販・育成された品種の耐病性を調査した。 |
|
普及技術 平成11年(1999年)水産試験場 水産試験場佐久支場
新しい農薬の魚類に対する急性毒性(H.11)魚類に対して、ユニックスZ水和剤は急性毒性があり、基準散布濃度で使用した場合でも魚類に被害を及ぼすおそれがあるので、使用に当たっては注意を要する。チェス水和剤の魚類に対する毒性は低い。 |
|
普及技術 平成11年(1999年)南信農業試験場
新しい農薬の蚕に対して薬害のなくなる安全基準日数(H.11)新しい農薬の蚕に対して薬害のなくなる安全基準日数はチェス水和剤が稚蚕壮蚕ともに7日マッチ乳剤が稚蚕壮蚕ともに60日以上、スピノエースフロアブルが稚蚕壮蚕ともに60日以上、ラブサイドベフラン粉剤DLが稚蚕壮蚕ともに20日、ユニックスZ水和剤が稚蚕壮蚕ともに20日、フェスティバルM水和剤が稚蚕壮蚕ともに15日である。 |