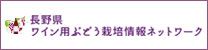天空のしずく(てんくうのしずく)開発ストーリー

令和7年に品種登録された長野県オリジナルの日本なし「天空のしずく」。大玉で甘く、日本なしで問題になっている複数の主要な病気に強いという特性を持っています。この品種が誕生するまでにはどのような物語があったのでしょうか。その裏側には、「南水」から続く品種開発に向けた研究の積み重ねがありました。
「南水」の誕生と強み
南信地域は古くから日本なしの栽培が盛んで、県下の一大産地となっています。この地域にある南信農業試験場で平成2年に日本なしの県オリジナル品種第1号として、南信州の「南」の字を冠した「南水」を開発・品種登録しました。「南水」は、果汁が多く糖度は14〜15%と甘味が強いのが大きな特徴で、果重は360〜380グラムとなる大玉の品種です。県単独で育成した日本なしの中では国内では最も栽培面積が広く、全国的にも知名度の高い品種です。
日本なしを栽培する上では黒星病と黒斑病に注意が必要です。平成18年頃に全国的に広く栽培されていた早生品種の「幸水」で、ナシ黒星病の発生が問題となりました(当時の栽培品種の中に黒星病に強い品種はなし)。いずれの病害も葉や果実に発生し、果実品質の低下や出荷ロスの増加につながります。
そのような中、黒星病に強い「南水」がなし産地の発展に大きな役割を果たしてきました。一方で、「南水」はナシ黒斑病には弱く、予防のためには丁寧な袋掛けが必要で、ナシ黒斑病に強い品種に対して一手間かけた管理作業が必要となっており、なし産地では黒星病と黒斑病の両方に強い品種が待ち望まれていました。
「南水」の次の品種を
南信農業試験場では黒星病と黒斑病の両方に強く、袋掛けの作業を省略できる品種を開発するため、「南水」を様々な品種と掛け合わせを行いました。その中から、ナシ黒星病の耐病性とナシ黒斑病への抵抗性を兼ね備えた品種が育成でき、令和3年9月16日に「天空のしずく」として出願が受理され、公表されました。
「天空のしずく」は収穫期が9月上~中旬と中生で、果実重は400~500gと大玉で玉揃いが良く、糖度は15%程度と高い良食味な品種です。今後、中生品種の「豊水」や「南水」に替わる品種として期待されます。
農薬の削減に向けた新たな潮流
農林水産省は令和3年に「みどりの農業システム戦略」を策定し、2050年までに化学合成農薬の使用量をリスク換算で50%削減する等の高い目標を掲げています。「天空のしずく」はナシ黒斑病に強いため袋掛けは必要なく、ナシ黒星病にも強いことから、環境にやさしい、持続可能な農業の先駆けとなることが期待できます。
「南信州日本なし産地再生プロジェクト」に向けて
「天空のしずく」という品種名は、1,300程の応募の中から“南信州を流れる天竜川“と“自然豊かな地域で育成されたみずみずしい梨”をイメージできる名称として選ばれました。数年後の市場デビューに向けて、現在、南信州地域では「天空のしずく」の生産拡大への取り組みがスタートしており、試験場では、高糖度でおいしい果実を省力・安定的に生産するための技術開発に取り組んでいます。
また、南信州地域では、生産者、農業関係団体、市町村、県機関などが一体となって「南信州日本なし産地再生プロジェクト」に取り組んでおり、「天空のしずく」はこのプロジェクトをけん引する一つの柱として期待されています。
日本なし育種のこれから
「南水」に始まった南信農業試験場における日本なしの育種は、担当する分野の垣根を超えた研究員達に綿々と引き継がれ、「天空のしずく」の開発に至りました。
今後も南信農業試験場では、既存品種の課題を解決するために先進的な選抜手法を駆使しながら、栽培しやすく美味しい日本なしの開発に取り組んでいきます。

【天竜川を望む南信州の風景】