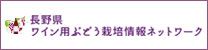小麦「ハナチカラ」と「しろゆたか」の開発開発ストーリー

長野県は小麦粉の年間支出金額順位が常に1位(総務省統計局の家計調査 長野市)であることからも分かるとおり、小麦粉を使った「うどん」、「おやき」、「すいとん」などの郷土料理を家庭で調理して味わう「粉食文化」が根付いており、長野県産小麦のほぼ全量が県内で消費されています。
このように小麦への関心が高い長野県において、その全県栽培面積の約60%を占める新品種が導入されました。そこで、当時農業試験場育種部で主担当として新品種の開発に従事した田淵主任研究員から紹介します。
長野県の小麦生産と品種開発の状況
長野県内で麦類は水田転作作物として水稲→麦→大豆の2年3作体系などで導入されており、小麦栽培面積は2,270ha(農水省公表値 令和7年2月28日公表)です。
小麦はその子実に含まれるグルテンと呼ばれるタンパク質の量によって粉の用途が変わります(下図参照)。

グルテンの質が弱く量の少ないものは薄力粉と呼ばれ、主に菓子用途として利用されています。同様に中程度の中力粉はうどんやおやきなど、強く多い強力粉はパン用途として利用されています。品種によってグルテンの質と量が異なるため、長野県内では消費者のニーズに合わせるために複数品種の小麦が栽培されています。例えば中力小麦ですが薄力粉用途にも使用できる「しゅんよう」、中力小麦として「しろゆたか」と「ユメセイキ」、強力小麦「ゆめかおり」、超強力小麦「ハナチカラ」と多くの品種が栽培されており、これらは全て長野県農業試験場で開発された品種です。
都道府県で麦類の品種開発を行っているところは少ないですが、長野県では明治31年から県内の在来系統の調査を始め、大正11年から優良な親同士の交配を開始しました。また、国の事業で昭和29年から大麦、昭和36年から平成22年まで小麦も含めた麦類の品種開発を行う指定試験地として東北南部から関東東山地域の中山間高冷地に適した品種開発を行ってきました。
〇 新たな超強力小麦「ハナチカラ」の開発
~春先の凍霜害と赤さび病被害軽減に向けた挑戦~
近年まで長野県では、長野県農業試験場で育成された国内初の超強力小麦である「ハナマンテン」という品種が長く栽培されてきました。グルテン含量が多く、製粉業者からの評価が高い品種でしたが、越冬性が低く、県内では春先の凍霜害に弱いこと、また、赤さび病(下図)に弱く減収につながることが大きな問題となっており、生産者から栽培性を向上させた品種の開発を要望されていました。

ハナマンテンに発生が多い赤さび病
このため、平成14年(2001年)に「ハナマンテン」を母とし、東北で開発された「ゆきちから」を父として交配を行い、令和3年(2021年)に「ハナチカラ」を開発しました。「ハナチカラ」は越冬性が高く、赤さび病にも比較的強い品種で、さらに「ハナマンテン」に比べて10%以上も収穫量が多く、栽培性に優れています。なお、品種名「ハナチカラ」は、「ハナマンテン」変わる超強力粉小麦であること、中華麺に適する強靭なグルテンを持つことから命名されています。
これまで「ハナマンテン」の収量性の低さに悩まされていた生産者の皆さんに喜んでいただける品種を開発でき、とてもうれしく感じています。

〇 病気に強い新たなうどん用小麦「しろゆたか」の開発
~土壌病害「コムギ縞萎縮病」への挑戦~
長野県ではうどん用小麦として「シラネコムギ」という品種が長く栽培されてきました。「シラネコムギ」は品質と栽培性で優れた品種でしたが、コムギ縞萎縮病という病気に弱いというデメリットがありました。このコムギ縞萎縮病は薬剤防除が困難な土壌伝染性病害で、越冬後に株全体が黄化し、発生が激しい場合は大きく減収する病気です(下図)。平成20年に長野県内で確認されてから県下各地で被害が増加したため、病害に強く品質も優れる新しい品種の開発が求められていました。

コムギ縞萎縮病を発病した小麦

健全な小麦
そのような状況において、平成18年(2006年)に「きたほなみ」を母とし、「キヌヒメ」を父として交配を行い選抜した、新時代の基幹品種となる「しろゆたか」が育成され、令和3年からは、県内で栽培を推奨する品種である「奨励品種」として栽培されています。この新品種は前述のコムギ縞萎縮病にも強く、短稈で倒伏に強く、やや多収という性質を持っています。また、「しろゆたか」という品種名が示す通り、粉及び生地の色が明るい白色であることも大きな特徴です。

今後の展望
品種の転換は生産者と実需者の両者に大きなメリットがないと進まないので、両者のご理解をいただくために関係機関の協力を得ることが大変重要となります。そのような状況の中で、令和6年産実績として「ハナチカラ」は435ha(全体の約20%)、「しろゆたか」は810ha(全体の約40%)で栽培されており、関係機関の協力を得ながら小麦の全栽培面積の約60%に関わる品種の転換を行うことができました。
また、交配から奨励品種となるまでに「ハナチカラ」で18年、「しろゆたか」で16年かかっているように、品種の育成には長い時間が必要です。遠い未来の動向を予測しながら、将来必要とされる品種を開発する難しい仕事ではありますが、今後は温暖化に伴って被害が増加している病害に強い品種の開発等を目標に、生産者や消費者に喜んでいただけるような品種の開発を行っていきます。

「ハナチカラ」
毛が短く、どっしりと実がつくことが特徴

「しろゆたか」
稈長は短いがたくさんの実をつける栽培しやすい草型

小麦育種試験ほ場の収穫作業風景
育種ではたくさんの品種を同じ条件で育てて、品質や収量を比較する必要があります。そのため小さな区画ごとに栽培、収穫して品質や収穫量を比較し、より優れた系統を選抜します。